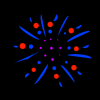 【第十章 絶望の淵から】
【第十章 絶望の淵から】❹❹❹藤井牧師の軌跡❹❹❹
| ① 入学の直前に | ② 「ロック、まかしたよ」 | ③ 二つの光を得て |
緒方理事長を中心とする福岡盲導犬協会と訓練センターの目的は、いうまでもなく一人でも多くの視覚障害者に盲導犬という伴侶を与え、生活の自立を助け、より幸せになってもらうことである。それを唯一の望み、やりがいとして日夜苦労しているわけだ。
だから、昨日までは閉じこもりがちだった視覚障害者の方々が盲導犬を与えられた日から生き返り、元気に暮らしはじめたという話を聞くと、スタッフは日ごろの苦労も忘れ、仕事の最大の励みとなる。脳出血で倒れた緒方を生死の境から生き返らせたのも、夢のなかに出てきた視覚障害者の笑顔だったことは冒頭に紹介した。
そんな人びとの中の一人、盲導犬によって新しい世界を見つけた福岡市東区、香住ケ丘バプテスト教会の名誉牧師、藤井健児さんを紹介しよう。福岡盲導犬協会の第一号盲導犬ロックの主人である。
入学の直前に
藤井さんは六十六歳、全盲である。小学校に入学する直前、猛スピードで走ったきた自転車にはねられ、左眼球が飛び出す事故にあった。ひき逃げだ。楽しみにしていた入学もだめになった。不幸はつづいて起こる。入院中だった父が、わが子の事故にショックを受け、二週間後に亡くなったのである。
左目の失明、入学の断念、父の死。三つの不幸で藤井家は失意のどん底に落ちた。
藤井さんは右の目を頼りに、一年おくれて小学校に行こうと思ったが、医師は盲学校をすすめた。残った目も、やがて光を失うだろうと予測したのだろう。悩んだ末に普通校をあきらめた。教師になったばかりの母親も藤井さんと一緒に盲学校に転任した。
藤井さんは福岡県立盲学校に旧制中等部三年まで在学したが、「見える右目と見えない左目。さいわい健常者と障害者の両方を理解できることを生かし、両者の橋渡しができる盲教育者になろう」と難関の東京教育大(現在の筑波大)付属盲学校高等部に進学した。ところが、教師への夢もふくらんだ卒業を目前にして、ついに頼みの右の目も緑内障で視力を失う。二十歳のときだった。
絶望の淵に落ちた。いっそ死のうと、何度思ったことだろう。生きていてもなんの希望があるだろう。自分が死ねば、負担をかけてきた家族も助かる。自分も苦しみから逃れられる。迷い、すさみ、もがく日々がつづいた。
そんなとき、ときたま訪れていた大学近くの教会でキリストの言葉を知った。 『私(イエス キリスト)は世の光である。わたしに従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ』
最初は、賛美歌を聞くのが楽しみで教会に行く程度だったが、肉体的、精神的絶望の中で、この言葉が心を捕らえはじめた。
もう目を治そうとは思うまい。失ったものを悔いるより、あるものに感謝しよう。目は失ったが、手も、足も、あるではないか。与えられたものを生かす人生にしよう。自分と同じ境遇の人びとのために生きていこう。このイエスの言葉は、今も藤井さんの名刺の裏にある。
ヘレン・ケラーに会ったのも、このころだった。昭和三十年、彼女が二度目の来日をしたとき、会って握手をする機会があった。またヘレン・ケラー奨学金をもらうこともできた。
教育者の道から信仰の道へ。志を決めた藤井さんは母や友人が引き止めるのを振り切るように東京から離れ、バプテスト派の西南学院大神学部を受験、ここでも、盲人の入学は初めてという難関をパス、五年間の勉学ののち宣教の道に入った。以来三十八年間、香住ケ丘教会の牧師として人びとに光を与えてきた。
「わたしは光を失い、光を得ました。しかも、得た光は二つ、信仰によって得た心の光と盲導犬という光です」
「ロック、まかしたよ」
藤井さんは小さいときから犬や動物が好きだった。童話『ロバータ、さあ歩きましょう』や『ぼくは盲導犬チャンピー』などを通して、盲導犬って、すばらしい、と思っていた。でも遠い外国や東京での話である。
失明してから盲導犬のことを家族や友人に話してみたが「日本では、まだ無理」と反応はよくない。しかし、いつか日本でも盲導犬が白杖に代わる日がきっと来ると信じていた。
チャンスが来た。『点字毎日新聞』で、東京の盲導犬訓練センターの若者たちが育てた盲導犬二頭を希望者に譲渡するという記事を読んだ。申し込むと運よく選ばれた。
ただ東京・小金井市まで行き、訓練を受けるため一カ月ほど寝泊まりしなくてはならない。教会の仕事もある。だが思い切って出発した。こうして藤井さんとロックは出合った。昭和四十七年一月、藤井さんが四十歳のときだった。
ロックは当時二歳、ラブラドール・レトリーバーのメス。薄いブラウン色で体高三十センチ、体重も約三十キロある堂々たる体格。その名の通り岩のように威厳のある犬である。そして無愛想。「よろしく」といっても、なでてやっても、「ふん、ちやほやするな」といわんばかりの知らん顔。心配になって訓練士に聞くと「そんな性格ですよ」。
ところが一時間ほど一緒に歩くうちにちロックの態度が変わってきた。疲れて座っていた藤井さんのひざの上にロックがあごを乗せてきたのだ。「あなたが自分の新しい主人だとわかったのですよ」
街の雑踏の中を二人は歩く。人と車、騒音、狭い道。街の一角を一周して、スタート地点にたどり着いたときのうれしさ。藤井さんは思わずロックを抱いた。「ありがとう」を連発した。介添えも杖もなしに、はじめて一人で歩くことができたのである。
藤井さんは「ロック、もう、君におまかせだ」といった。ロックはちょっと主人の方を見て「まかせときなよ」と応えた。藤井さんは、岩のような信頼を感じたという。
二頭のうちのもう一頭はシェパードで、大阪から来た女性が相手だった。この女性は杖一本で何キロでも歩けるという元気な人だったが、自分のカンを信じすぎて、「あほ、なにしとんね」と犬をしかり飛ばしながらどんどん歩いていく。犬はみるみる元気を失い、結局、二人の婚約は不成立になった。
「犬にまかせることが大切なんです。犬にも自尊心がありますから」
二つの光を得て
藤井さんとロックが福岡空港に帰ると空港は大騒ぎだった。テレビや新聞の報道陣が大勢押しかけ、記者会見をするという。九州では最初の盲導犬というので物珍しいのである。
迎えに来た家族は藤井さんがなかなか出てこないので心配していたが、待合室のテレビに夫とロックが映っているのを見て、びっくり。出発するときは「顔を傷だらけにして帰ってくるのでは」といって見送った家族だが“時の人”になって帰ってきたのである。西鉄が帰りの専用バスまで用意して、自宅に着くまで記者の質問攻めがつづいた。
記者会見には西鉄関係者も出席し「バスや電車にも自由に乗っていただくため一部規則を変えました」といち早く盲導犬対策をとったことを報告した。乗り物のことは一番心配していたので、うれしい提案だったが、ちょっとおかしくもあった。昨日までと様変わりだったから。
しかし、その後も、いざ街に出てみると多くの障害にぶつかった。国鉄時代のことだが、汽車に乗るには一週間前に乗車申請書を出し、何月何日の、どの列車に乗る、犬には口輪を付ける、といった約束をさせられた。タクシーに嫌がられたことも少なくない。最近は厚生省の通達もあって、そんなことはなくなり、改善されたという。
九州の第一号盲導犬ロックは八年半後、腸閉そくで死んだ。
「痛かったろうに、最後まで吠えたり泣いたりしなかった。かわいそうでならない」
藤井さんはロックのあとローリー、そして現在は三頭目のセイルを使っている。犬にも個性があって、無愛想なの、照れ屋、お茶目とさまざまである。だが、どの犬も、しかられるのと怒られるのとの違いは敏感に感じ取る。明らかに犬が失敗したときにしかると「悪うございました」と平身低頭するが、主人の方が感情的になって怒ったときは「なぜ、怒られるのか」といった態度で横を向く。
「普通の犬や動物は条件反射で反応するが、盲導犬は愛情に反応するのです」 セイルは教会の中に入ると、シッポを振るのをぴたりとやめる。藤井さんと一緒に壇上に上がると、ただちにダウン(伏せ)、お祈りの間は、足を組んで顔を床に着ける。「セイルもお祈りしているのでは」と思っている人は多い。そして最後の「アーメン」になると「さあ終わった」と命令を待つ形をとる。
セイルは、おやすみの時間は藤井さんの書斎とガラス戸一枚へだてた犬舎にいる。藤井さんが室内での用事のためにイスから立ったときは動かないが、外出のために立ち上がったときは、さっと立ち上がるという。
藤井さんは、じつに若々しい。この人が視覚障害者かと思うほどである。姿勢もしゃんとして笑顔を絶やさず、声も大きく、はりがある。絶望的な過去の影をまったく感じさせない。信仰から得た強さ、やさしさというものなのか。「私は二つの光を得ました」。信仰の力に加え、盲導犬という好伴侶を得て、光の中を歩みつづけることだろう。
福岡盲導犬協会が、これまでに貸与した盲導犬は九十一頭だが、それを受け取った一人一人の視覚障害者が藤井さんと同じような苦悩と感動の過去を刻んできたに違いない。それを思うと、心の底から「皆さん元気を出して。さあ、愛犬とともに歩こう、自立の道へ踏み出して」と願わずにはおられない。
 次のページへ。
次のページへ。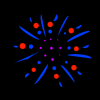 目次へ戻る。
目次へ戻る。 トップページへ戻る。
トップページへ戻る。★ Copyright(C) 2001-2006 無断転載を禁じます
。