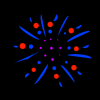 【第六章 二つの闇】
【第六章 二つの闇】❹❹❹視覚障害者の悩み❹❹❹
| ① 公民館もお断り | ② 「ほら、犬の毛が」 | ③ 五十年の遅れ | ④ 寄付をはばむ税制 |
| ⑤ 犬は一段下? | ⑥ 狭い家屋も普及の壁 | ⑦ 三本足のサーブ |
公民館もお断り
「視覚障害者の一歩前を盲導犬が行く。そして二歩先には社会の無理解が待っている」といわれる。
盲導犬を育成する仕事のほかに、もう一つ、緒方たちの前に立ちふさがる問題があった。視覚障害者や盲導犬に対する世間の認識である。
せっかく盲導犬を連れて歩けるようになっても社会が温かく受け入れなくては何にもならない。偏見とまではいえなくても「盲目」や「犬」にたいする違和感は、日本人にはなお根強いものがある。これは盲導犬の普及以上の難問だった。 最近はかなり改善されたが以前はひどかった。盲導犬を「どうもうけん(獰猛犬)」と勘違いする人さえいたころである。社会の理解は十分ではなかった。
今から二十年ほど前のことである。
JR、当時の国鉄などは比較的に早く、受入れを認めた方だが、それでも視覚障害者が盲導犬を連れて乗車するときは、何日の、どの列車かを一週間前までに申請書に書いて申し込まねばならなかった。電車やバス、航空機も、おおよそ受け入れる方向に進んでいたが、「原則として口輪を着けること」と条件を付けるところが多かった。盲導犬はかみつかないように訓練されていることさえ理解されていなかった。
タクシー会社は「陸運局の指導で乗せるようにはなっているんですが、怖がる運転手もいて……」といった状況。ホテル、レストラン、デパートなどは大手は受け入れたが、多くは消極的だった。病院は衛生上の理由で、全面的に認めていない。
ある市の公民館で、盲目のランナー漢小百合さんが盲導犬カンナを伴って壇上に上がろうとして、職員に「犬を上げてはいかん!」と断られたこともあった。公共施設でさえこんな調子だった。
「ほら、犬の毛が」
食べ物をあつかう食堂や店では入店お断りが目立っていた。新聞にも「レストランで入店を断られました。目の代わりといっても犬は犬。他のお客が嫌がりますから。あなたの洋服に、ほら、犬の毛が一本着いているではないか、といわれました。毎日ブラッシングしているのに。悔しくて、悔しくて」といった投書が出たりした。
「他のお客様が嫌がりますから」は、いろんな所でしょっちゅう言われる言葉だ。「わたしが嫌です」といわれるより余程腹立たしいとユーザー(使用者)はいう。
レストランで「お客様が嫌がりますから」と入店を断られたユーザーが店内の客に向かって「皆さん、私たちが入ったらほんとに困りますか? 正直な気持ちを教えてください」と言ったところ、客の一人が「そんなことはありません。どうぞ入ってください。皆さん、いいですね?」。すると、皆が立ち上がり拍手して迎えた、といった記事も紹介された。
東京都練馬区にある盲導犬の育成団体「アイメイト協会」が東村山市に移転しようとして、住民から「鳴き声、においが心配。犬の毛がアレルギーを引き起こす」と反対され、宙に浮いているという実態もある。
最近、アイメイト協会が行った「盲導犬使用者の人権侵害にたいする実態調査」によると、アンケート回答者二百八十六人のうち約七〇㌫が宿泊施設で、約九五㌫が飲食店で利用拒否された経験を持つ。三、四割は交渉によって利用にこぎつけているが、特別料金(米国やカナダでは違法となる)を取られたり、条件を付けられたりしている。
緒方自身も何回も経験している。ある視覚障害者が飯塚市のホテルで行われた友人の結婚式に出席しようとしてホテル側から断られた。緒方が電話で説明したが、らちが明かない。飯塚まで出向いて話し合い、やっと納得させたこともある。拒否、説得、納得。その繰り返しを何度経験したことか。
視覚障害者は「盲目」に加えて「世間の無理解」という二つの闇の中を歩まねばならなかったのである。
「最近は、ずいぶんよくなった。公共施設、デパート、ホテル、レストラン、まず心配はなくなった。一部では残っているが」
あるスーパーは『視覚障害のお客様に対するお買物対応ハンドブック』という従業員向けの指導書を出している。
・視覚障害者に気付いた従業員がまず声をかけ、対応する。
・買物対応は支配人、店長、総務課長、またはそれらに指名された従業 員があたる。
・(盲導犬を連れたお客様には)エスカレーターや階段を利用する場合 は、いったん止まり、「上がります」とお知らせし、案内係の腕を持 っていただいたままで同じステップに足が乗るようにする
などと、こまかなマニュアルが述べられているが、肝心なのは受け入れる側の心であることはいうまでもない。
五十年の遅れ
わが国は、盲導犬の育成では欧米より三十年遅れ、社会の受け入れ態勢では五十年遅れているといわれる。海外はどうか。
東京の視覚障害者がこんな経験をしている。
シカゴからニューヨークに向かう列車でのこと。ニューヨークまでは十七時間もかかると聞いて、犬のトイレのことが心配になり、車掌さんに相談したところ「途中、二回のトイレですね。オーケー、その時間になったら、あなたの席に来ますから」と快く引き受けてくれた。
そろそろトイレの時間と思っていると、車掌があらわれ、駅でもない所に列車を停車させ、“二人”を降ろして近くの草むらまで案内した。「時間は十分あるから、あわてなくてもいいですよ」といって、ビニール袋まで用意して待っていてくれたという。二回目も同様だった。しかも、驚いたことに、予定外の二度の停車にもかかわらず、乗客は、なぜ列車が停まったのかさえ知ろうとしなかったという。
アメリカにはADA(『障害を持つアメリカ人法』)があって、これにより盲導犬同伴者は守られている。
東京経済大学の竹前栄治教授が盲導犬を伴って渡米したときの体験を新聞(朝日)に書いている。
盲導犬使用者にたいする空港でのターミナルサービス(出入国・税関・検疫手続き、座席の手配、盲導犬の排便場所への誘導など)もじつに行き届いて感心したという。ホテルやレストランも盲導犬を白杖感覚で受け入れ、客も犬を見て「かわいい」とか「ナイスドッグ」といってほめても、なでたり、食べ物を与えることはなく、ごく自然に対応する。
そうはいっても、盲導犬を拒否するケースが皆無ではない。六十五年の伝統を誇るニュージャージー州モーリスタウンのシーイング・アイ協会(盲導犬協会)を訪れたとき「断られるようなことがあったら、これを示すように」と名刺大のカードを渡された。それには、こう記されていた。
「盲導犬はペットではありません。誘導の役割を果たすために科学的に選ばれ、訓練されています。使用者は盲導犬の扱いを完全に習得しています。ADAおよび州法は、盲導犬使用者にたいして公共の宿泊施設・交通機関の利用を保障しています。それらに入ることやサービスを拒否すれば違法となります」
実際、国立公文書館に入ろうとして受付嬢が拒否しようとしたので、このときとばかりカードを見せようとすると、上司が駆けつけてきて「連邦法のことを知らないのか」と受付嬢をしかり、一件落着となった。
あるレストランでは、テーブルクロスの下から出ていたしっぽだけを見て「ペットはだめ」といわれたが、盲導犬とわかると、ただちに謝り、快く受け入れてくれたという。盲導犬使用者の権利法はここまで浸透しているのである。
海外旅行から日本に帰ってきたユーザーは、口をそろえて成田空港の職員の対応の悪さを指摘するが、日本に帰って来たとたん、内外の差を、さっそく見せつけられるということだろう。
寄付をはばむ税制
さて、その日本の実態はどうか?
第一に、盲導犬に関する法律は、道路交通法に若干の保護規定があるくらいで法整備はなきにひとしい。寄付をしやすいように欧米では、寄付にたいする減免措置があるが、これも日本は遅れている。
有吉佐和子さんがベストセラーになった『恍惚の人』の印税一億円を社会事業に寄付しようとしたが、税制がそれを許さず、いったん個人の所得となったものは、寄付しようがしまいが累進税率によって七、八〇㌫を税務署に持っていかれるということがあった。
黒柳徹子さんの『窓ぎわのトットちゃん』のときも同じ。黒柳さんは出版社からの印税振り込みをストップしてもらい、その代わり社会福祉法人トット基金なるものを急いで設立して、そこが印税を受け取る形にして、ようやく印税を福祉事業に寄付することができたという。
日本で盲導犬育成団体の「特別公益増進法人」化が認められたのは、つい五年前のことである。盲導犬育成の事業資金は八、九割がた企業、団体や個人の寄付に頼っているが、企業は、税控除にならないと知ると寄付を取りやめるケースが多く、関係者は泣かされてきた。何度も厚生省や大蔵省に陳情に行き、やっと実現するまでに十年もかかっている。
日本の福祉事業は寄付に頼らざるをえないのに、その寄付への対応がこんな実態なのである。平成十年三月、NPO法(特定非営利活動促進法)がやっと成立したが、減免措置は見送られた。緒方は福祉政策に不満である。
「人間だれしも、一生に一度は世のため人のために、何かをやりたいと思うことがあろう。生涯かけてためたお金、あるいは予期しなかった収入、そういうお金を、自分の意思を生かす形で社会事業に投じたいと考える人は少なくあるまい。それが阻まれるようでは福祉は死んでしまう」
犬は一段下?
「盲導犬という動物がからんでくると日本の社会福祉はもっと問題が多い。これは視覚障害者福祉にたいする考えだけでなく、犬そのものにたいする国民の考え方の違いもあるのではないか」と緒方はいう。
たとえば、アメリカ人には犬とともに開拓をすすめ、犬によって外敵から守ってきた開拓の民の血が流れている。イギリスでは、犬は貴族の象徴であった。より良い犬を持つことが権威を高めた。何百年、何千年、犬との共存をつづけてきた歴史を持っている。
そんな歴史があるから盲導犬への配慮もしっかり根づいており、訓練センターはもちろん、盲導犬の理解を深める学校などにも財政面からも支援している。
一方、日本人は、犬を可愛がる人は多いが、欧米に比べると、まだペットの域を出ていない。犬にたいする抜きがたい侮蔑の歴史がある。「犬畜生」「夫婦喧嘩は犬も食わない」「警察の犬」「シッポを振るな」。犬のつく言葉にろくなものはない。
ゴルドン青年の来日をきっかけに、わが国でも盲導犬を広げようという声が起こったときも「犬と起居を共にすることは盲人の地位を犬と同じにおとしめることだ」と血判状を持って反対した視覚障害者もいた。
「犬を人間より一段下と見るようになったのは徳川綱吉からでは」
とは緒方の考察である。
犬公方、徳川綱吉の生類哀れみの令の反動ではないか。あのときから日本人に犬に対する嫌悪感が生まれたのではないかというのである。
レストランなどが盲導犬を断るときの決まり文句は「お客さんが嫌がりますから」だが、ほんとに嫌がっているのか。店側が、反射的にそう言ってるだけではないのか。犬と聞いただけで生じる拒否反応が日本人のどこかにある、と。一つの見方だろう。
世間一般だけでなく、視覚障害者自身や家族にも、そんな感覚があるという。盲導犬を勧めても、犬と一緒に歩くのを恥ずかしがる人は少なくないらしい。
「家族の中に目の見えない人がいると、それを恥として外に出さない。家に囲ってしまう。外に出せば障害者も自立への一歩が踏み出せるし、家族も助かるのに。本人や家族たちが、外に出よう、社会にかかわろう、と考えたときから盲導犬への理解は深まり、もっともっと活用されるようになる」
「盲導犬は高いお金を払って買うものと考えている人も少なくない。えさ代も高くつくと。ペットと間違えている。もっとPRしなくては」
さすがに最近は、こんな家族は減ってきたが、まだまだ理解していない人がいるようである。
狭い家屋も普及の壁
しかし、事情はもっと複雑なのかもしれない。
欧米では、早くから犬を室内で飼い、犬と生活を共にするという共存関係が築かれている。犬に対しては小さいときからきちんとした「しつけ」をするのが飼い主の義務であり、責任とされている。だから、そのような犬は、当然マナーを心得た“市民犬”として、人間社会に仲間入りすることが許されている。盲導犬でなくても乗り物やレストランなどに自由に連れていくことができる。
しかし、日本の盲導犬の歴史は、わずか数十年。盲導犬という外国で生まれたものが伝統的文化の色濃い風土のなかに突然、舞い降りてきたようなものだから、あちこちで反発や摩擦が起こるのは無理もないことかもしれない。
早い話が、日本の家屋の構造も盲導犬の普及をさまたげる原因となっている。欧米では犬を家の中に入れてベッドの横に座らせる。たたみ文化の日本では、そうはいかない。主人はベッド、犬は離れた場所の箱の中、では、二人は完全に一体化することはできない。寝起きを共にしてこその盲導犬なのだから。
盲導犬がほとんど欧米に限られ、アジア地域にはあまり普及しないのも、この家屋の構造、犬と人との関係が影響しているのではないか、と緒方は考えている。(韓国、台湾では近年、盲導犬訓練所が登場した)
この点について福岡県盲人協会の田代浩司会長の意見を聞いてみた。
「視覚障害者の多くが盲導犬を使いたいと思っている。だが二つの事情が妨げになっている」
一つは、犬との共同訓練で一カ月近く、仕事から離れなければならないこと。視覚障害者の多くはハリ灸、マッサージなどの職についているが、お得意様のお客を逃してしまうことになる。
もう一つは家の問題。視覚障害者の経済状態はさまざまだが、皆が犬を中に入れて飼えるほどゆとりのある家に住んでいるわけではない。
「盲導犬を飼うために、もっと広い家を借りようとしても、目が不自由と聞くと、火事を心配して貸してくれない家主は少なくないのです」
まして、犬と一緒に住むと聞いただけでしり込みする家主はまだまだ多いのである。
盲導犬事業は寄付で、というのが一般的になっているが、行政もそろそろ本腰を入れて助成すべきではないかとの声も上がっている。
福岡県鞍手町では今年から町内の盲導犬使用者に飼育費の半額を助成することにした。無償貸与とはいってもえさ代、医療費などが毎年、十二万円ほどになるからという。それが負担になって盲導犬をあきらめる人もいるので助成に踏み切った。市町村が使用者個人を助成するのは初めてで、まだ例外的な措置といえよう。
盲導犬を育成すればよいというだけではすまない問題が余りにも多い。視覚障害者の前には依然として“二つの闇”が立ちふさがっている。
三本足のサーブ
盲導犬の理解がなかなか進まないなか、昭和五十七年、盲導犬のイメージを一気に高めるニュースが大きく報道された。今では盲導犬の代名詞にまでなった「三本足のサーブ」である。
サーブ(シェパード)は同年一月、岐阜県郡上郡の国道で、前から突っ込んできた暴走車から主人をかばい、重傷を負った。安楽死させるしかないと思われたが、事故を知った全国の子どもたちから「身代わりとなったサーブを助けて」との訴えが殺到したため左前足を肩から切断して命を助けた。
その後、児童本や社会科副読本にも載った。子どもを中心としたサーブあての激励文は三千通を超え、寄金も四百万円にのぼった。首相官邸で中曾根首相から功労賞のメダルをかけてもらったり、銅像を建ててもらったり、忠犬ハチ公、南極犬のタロやジロと並ぶ英雄として、その感動物語は海外にまで伝わった。
もう一つ、サーブは、わが国の盲導犬史上、注目すべき成果を残した。重傷を負ったサーブに自動車保険の対人保険の適用が認められ、飼い主に三百二十万円の保険金が給付されたのである。飼い主は「盲導犬はわたしの体の一部」と主張していたが、これが認められたもので、画期的なことだった。世間が「盲導犬はペットではない。人の体の一部なのだ」ということを認識する大きなきっかけになったのである。
 次のページへ。
次のページへ。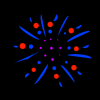 目次へ戻る。
目次へ戻る。 トップページへ戻る。
トップページへ戻る。★ Copyright(C) 2001-2006 無断転載を禁じます
。