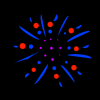 【第三章 無給勤務、十二年】
【第三章 無給勤務、十二年】❹❹❹福岡盲導犬協会へ❹❹❹
| ① 隠居暮らし、一転 | ② 鶴喜代二の情熱 | ③ 愛と光の十字運動 |
隠居暮らし、一転
流通センターの専務理事を辞めて、しばらくは家にいた。もう第一線での仕事は終わったと思っていた。二年ほど経ったころだった。“おやじ”こと鶴喜代二元正金相銀社長から電話で呼び出された。
「まだ六十九だろ。おれより若いのに、もう隠居か」
中央区大名町の料亭、稚加栄に行ってみると石村貞雄さん(元福岡市議会議長)と二人がいた。鶴元社長は西銀を辞めた後の昭和五十六年に自分が設立した九州盲導犬協会(財団法人福岡盲導犬協会の前身)の理事長、石村は副理事長をしていた。何かありそうな気配である。
大いにビールを飲み、何時間もたったのに鶴は肝心の用件を切り出さない。しびれを切らして
「おやじさん、なにか用事が……」
と言いかけると、石村副理事長が
「なにか用事とは何な。頼まれ事の中身を聞かんとOKでけんとな? あんたは鶴さんの弟子じゃろもん」
新聞記者出身で博多っ子まる出しの石村副理事長はそういうものの言い方をする男だったが、それにしても無茶な話ではある。用件も言わぬ前からOKせよという雰囲気なのだ。さすがの緒方も面食らったが
「わかりました。なんかわからんけど引き受けましょう」
と言ってしまった。
「盲導犬協会の専務理事をやってくれ」と聞いて驚いた。
盲導犬? 自分が所属していた舞鶴ライオンズクラブが協会に盲導犬を寄贈したことがあったので若干の知識はあったが、盲導犬のことは詳しくない。
「盲導犬ちゃ、いったい、どんなものですかな」という質問に鶴理事長は「それは、おいおいわかる」というだけで直接答えず、
「ただ、ゼニが少々いる。一億ほど集めにゃいかん」
盲導犬協会は寄付でまかなわれている。理事長や専務の仕事は、とにもかくにも金集めなのである。浄財集めと聞いて、
「どうも給料なんかもらえん仕事のごとありますな。専務理事が給料をもらって人様から寄付をもらい歩いては筋が通らんごとある。無給でやりましょう」
これには二人とも驚いたが、緒方が奉仕を信条とするライオンズ会員ということを知っているので「好きにすればよか」と承知した。
勤務の時間だけは自分の自由にしてくれ、という緒方の二つ目の条件もかなえられたが、有無を言わせない強引な説得にまんまと成功した二人は肩の荷を下ろして帰っていった。後には、無給で働くことになった緒方が残った。
「流通センターのあとは盲導犬か。もっと人の役に立てということだろう」
流通センターを辞めるとき、この団地に進出していた繊維卸しのモリメンから「副社長で来ないか」といわれていた。数社からも誘いがあった。しかし、そんな気はなかった。
「間もなく古稀を迎える。これを境に引っ込もう。戦友会、校友会、ライオンズクラブの世話のかたわら温泉旅行でも楽しんで。妻にも長い間、苦労かけてきた」
それが一晩で覆ってしまった。
銀行人として一応勤めあげ、あとは悠々と余生を楽しむことはできる。しかし、いつも金を相手に計算や根まわしのことばかり考えてきた仕事にどこか物足りなさはあった。視覚障害者の支援という弱者に手を差し延べる仕事をしてみるのも悪くないなと思ったのである。
敬愛する故人、貝島義之は常々、緒方に
「ライオンズクラブは、その精神において企業論理とまったく相反する団体だ。だから入会せよ」と言っていたという。企業人は儲けに精を出すだけでなく、利益を社会に還元すべきだという戒めである。
「金相手の商売から人間相手の仕事へ」。そう考えると心は落ち着いた。第二の出発という感慨がわいてきた。
「このおれが今から盲導犬の仕事を始めると言ったら、妻はびっくりするだろうな」
無給は十二年ほど続いた。
「あなたはそれでよかろうが、それじゃ、あなたの後の理事長になり手がないから」という人がいて、一昨年から盲導犬訓練士の初任給並みの十五万円程度の手当てを頂戴している。
さらに緒方は、このとき六百万円を提供した。鶴理事長が協会をつくるとき一千万円を出したと聞いたからだ。そのころ協会は任意団体から財団法人に切り替える準備をしていた。協会の財政基盤を整える必要に迫られていた。それも多くは個人の負担である。
緒方は息子たちに譲っていた春日原と久山のゴルフ会員権を取りもどして売り、六百万円をひねり出した。
緒方が無給で働くことになったのは、一つは心意気、鶴おやじへの恩返しの気持ちもあったのだが、最大の理由は彼がライオンズ会員だったことだろう。
奉仕団体のライオンズクラブは「金のあるものは金を、働けるものは労力を、知恵のあるものは知恵を」がモットーである。「無給」も「六百万円」も貧者の一灯のつもりだった。
「協会は浄財でまかなっているのに給料などもらえないよ。それに無給には無給の良さがある。友人に寄付を頼むにしても、こっちが無給でやってるから強く出れる。無給で仕事するというのは気持ちいいもんです。やったもんじゃないとわからん、わからん」
と笑う緒方だが、最近の低金利だけは頭が痛い。銀行の退職金も心細くなってきたようだ。
「何の欲しいものもなし。暮らしていくには十分。かみさんが食わしてくれるでっしょ」
鶴喜代二の情熱
緒方と盲導犬の出合いはひょんなことから始まったが、鶴喜代二と盲導犬の出合いも、ふとしたことからだった。話は二年ほど逆のぼる。
西日本銀行相談役をしていた鶴が東京で開かれた全国銀行協会の懇親会に出席したとき、隣に居合わせた関東地区の銀行幹部が、さかんに盲導犬の話をする。盲導犬の役割、企業とメセナ、銀行も社会の役に立つことをすべき時代だと。
鶴相談役は盲導犬をテレビか本で見たことはあるが、知識はない。
「九州には盲導犬がいないのですか。そりゃ寂しいですね」
その幹部がいろいろと説明するのを聞きながら、鶴は心に期するものがあったようだ。鶴自身、目が不自由だったのである。だから
「盲導犬を使うと視覚障害者の行動の幅はぐっと増える」
「盲導犬は白杖と違って視覚障害者の孤独をいやしてくれる。犬というより人間の体の一部なのです」
といった言葉がじつによく理解できた。
白い杖、点字ぐらいしか知らなかった鶴に“盲導犬”という言葉とイメージが、じつに新鮮なものとして脳裏に描かれたであろうことは想像にかたくない。
盲導犬協会は当時、北海道、東京、栃木、名古屋、京都、大阪にあったが関西以西にはなかった。もちろん盲導犬を育成する訓練センターも。
福岡に帰った鶴喜代二は、さっそく盲導犬協会の設立に向けて活動をはじめた。鶴は敬虔なルーテル教会の信徒で、日頃から社会奉仕を心がける企業家としても知られていた。
まず九経連会長をしていた財界の総帥、瓦林潔氏(故人、元九州電力社長)に話すと「そりゃ九州の恥じゃ」と協力を約束してくれ、はやばやと九電が盲導犬訓練センターの土地を提供する話がまとまった。都市部にある盲導犬協会はどこも訓練センターの用地確保に苦労したものだが、この点、福岡は幸先よいスタートが切れたのだった。
協会の理事長には鶴、副理事長には石村貞雄が就任、この二人を中心に理事、顧問、相談役を依頼していった。メンバーには瓦林、亀井光福岡県知事、進藤一馬福岡市長らのほか福銀、西銀、岩田屋など地元財界のトップをずらりと並べた。瓦林会長の力が大きかった。
盲導犬の性能に詳しい九州大学の稲田朝次教授、はせがわ仏壇の長谷川才蔵社長、博多町人文化連盟の西島伊三雄理事長らの名前もあった。総勢四十五人。事務所は市内大名町の一室を借りた。こうして他の協会に比べて特徴的な財界主導の協会が形を整えた。
そして昭和五十六年二月二十五日、西日本新聞国際ホールで任意団体九州盲導犬協会の発会式が行われた。まだ任意団体だったが、関東、関西地区に遅れること八年、西日本地区にはじめて盲導犬育成の拠点となるべき組織が誕生した。しかし、できたのは形だけ。行く手には多くの困難が待ちかまえていた。
愛と光の十字運動
当時の盲導犬の実態はどうだったのか。
盲導犬の頭数は、アメリカが約一万頭、イギリスに約五千頭。日本は今でこそ約八百頭いるが、当時は九州に八頭、福岡県下には三頭しかいなかった。
それも東京や栃木の訓練センターに育成を委託していたので、犬を希望する人は、そこまで出かけ、犬と一緒に訓練を受けるため三週間ほど寝泊まりをしなければならなかった。これは大きな障害だった。仕事を持っている人が三週間も空けることはとても難しいこと。泣く泣くあきらめる人も多かった。
「なんとしても自前の盲導犬訓練センターをつくり、九州や中国の視覚障害者に、せめて毎年十頭ずつは提供していきたい」
先立つものは資金である。行政は当てにならない。盲導犬育成に国や地方自治体がお金を出すなんて、とても考えられない時代だった。企業や団体、一般市民の善意の寄付に頼るしかない。訓練センターの建設費は約七千万円。年間の維持費が約五千万円。暗中模索の旅が始まった。
市民が盲導犬のことをあまり知らないころである。まずは「お祭りで世論を盛り上げよう」と盲導犬キャンペーンに取り組んだ。
五十六年五月、西日本新聞国際ホールで開かれた『盲導犬愛と光の十字運動』の決起集会では、鶴理事長が「九州には八万人の視覚障害者がいるのに盲導犬はわずか八頭しかいない。福岡はたったの三頭です」とあいさつ、全国盲導犬協会連合会の吉留路樹理事が「盲導犬の空白地帯、九州に、福岡に一頭でも多くの盲導犬を。何万という人がそれを待っている」と協力を訴えた。
さっそく朗報があった。地元、舞鶴ライオンズクラブが設立十周年を記念して盲導犬八頭の寄贈を申し出て、集会の席上、目録が鶴理事長に渡された。幸先はよかった。
アトラクションとして東京から連れてきたシェパードの盲導犬アリ号の実演が披露され、指導員の指示で落ちついた動きを見せる盲導犬に参加者は感心した。 「盲導犬への命令はすべて英語です。日本語だと方言やら敬語があって、たとえば、主人が『座れ』といい、妻が『お座り』といったのでは犬は理解できないですよね。だから座れは『シット』です」
そんな話を聞きながら参加者は盲導犬への理解を深めていった。そのときの模様を伝える新聞記事の見出しに「盲導犬は英語がわかる!」とある。記者自身が珍しがっていた。
マスコミも多くの記事を書いてムードを盛り上げた。たとえば西日本新聞は一面のコラムで、こんなふうに取り上げている。読者に犬と人間とのきずなの深さを説き、そもそも盲導犬とはどんな犬なのか、初歩的に説明していて当時の状況をしのばせる。
《ずいぶん以前、ビットリオ・デ・シーカ監督の『ウンベルトD』(1951年)という映画があった。老人と小犬の物語である▼老退職官吏の主人公は、いつも小犬と一緒である。彼の友達は、この犬と、下宿の娘しかいない。生活に困窮した老人は、小犬とともに列車に飛び込もうとし、愛犬の悲鳴でわれに返る。犬は老人の生きる支えであり、命を助ける存在でもある。喜び、孤独、すべてを老人と犬は分け持った。犬は人間に一番身近で、忠実な友達である▼盲導犬は利口なこと、記憶力、判断力に富み、神経が鋭敏であって、かつ大胆なこと。シッポを踏まれてもほえない忍耐強さなどが必要とされる……》(昭和五十六年五月二十七日「春秋」)
一方、街頭募金も大々的に行われ、ようやく「視覚障害者に盲導犬を」のムードが広がっていった。
ところが、運動に水を差すような残念な事態が起こった。
盲導犬は無償貸与なのに協会の事務局長がユーザー(盲導犬使用者)からお金を受け取るという不祥事が発生したのである。これには鶴理事長も参った。浄財を預かるものとして絶対に起こしてはいけないことだった。善意を寄せていた市民、積極的な支援を行ってきたライオンズクラブなど各団体からも浄財の使い方に疑問の声が出た。協会の信用は揺らいだ。
どうして協会の名誉を回復するか。とにかく協会のイメージを一新しなければならない。考えた末に鶴理事長が出した方策が、任意団体の九州盲導犬協会を財団法人にし、組織を確立して出直すこと、もう一つが適任の専務理事を見つけることだった。
専務は事務局のかなめである。人使いがうまく、正義感があり、しかも経理に明るい男。思い当たったのが正金相銀時代のかつての部下、銀行員からははみ出したような男、緒方だった。緒方を入れて明朗会計のイメージをアピールする。そして新たな財団法人として福岡盲導犬協会を設立、心機一転をはかったのである。
こうして「稚加栄の夜」の一件になるのだが、それを聞いて、緒方は窮地に陥った“おやじ”を救い、協会の信用を取りもどすために、ひと肌脱がねばならないと思ったのである。緒方が協会入りを承知したのも、一つは、そんな事情からだった。無給を申し出たのも「前任者が迷惑をかけた。せめて償いに」という思いがあった。
緒方は就任すると、まず自分が所属していた舞鶴ライオンズクラブに行って頭を下げ、寄付の継続と協会への協力を頼んだ。緒方にはつらい初仕事だった。
緒方は銀行マンから盲導犬育成へ、百八十度の方向転換をして、残る人生を視覚障害者の福祉に捧げることになった。
 次のページへ。
次のページへ。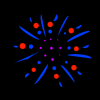 目次へ戻る。
目次へ戻る。 トップページへ戻る。
トップページへ戻る。★ Copyright(C) 2001-2006 無断転載を禁じます
。