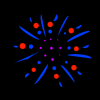 【第二章 「おれは炭鉱屋だ」】
【第二章 「おれは炭鉱屋だ」】❹❹❹正金相銀時代❹❹❹
| ① シュイホァン先生 | ② ケンカ相手は永久の仲 | ③ 仕事は心意気 |
| ④ 選挙応援する支店長 | ⑤ 難事業への挑戦 |
シュイホァン先生
昭和十三年、緒方は明治大学を卒業すると久留米騎兵隊第十二連隊に入隊、トップで予備士官学校に合格した。支那事変が始まっていた。中隊長として実戦も経験、命を拾うようなことも何度かあった。中尉まで進んだが軍隊は四年半で除隊した。
貝島義之氏のすすめで、中国に進出していた貝島炭鉱に入社、河北省にあった貝島炭鉱井径炭坑に就職した。
貝島義之は、五高、東大時代は佐藤栄作元首相の友人で、のちに貝島炭鉱に養子として迎えられ、社長や福岡商工会議所副会頭などを務めた人物である。大臣や知事も一目置くほどの実力者だったが、緒方の母方の遠い縁筋にあたる。緒方の後ろ楯となり、大きな影響を与えた。後年、緒方がライオンズクラブで奉仕の精神を身につけたのも貝島の感化によるものだった。
緒方の石炭稼業は敗戦をはさんで約十年に及んだ。中国では、炭鉱労務の仕事をしたが、憲兵とやりあったり、暮らしを共にした中国人労務者から「シュイホァン(緒方の中国読み)先生」と呼ばれたり、強いものとケンカし、弱い立場の人に気をくばる気風は、ここでも発揮された。
敗戦で混乱と憎悪が渦巻く時期が続いた。周りの者が戦犯で拘引されたりしたが、緒方はさいわい、昭和二十一年二月、妻、房子さんとともに引き揚げることができた。三十一歳だった。
本土に引き揚げた緒方は貝島炭鉱から出向して九州石炭鉱業協会に入った。肩書は整員係長。炭鉱労働者を集める仕事である。いわゆる労務屋。熊本、鹿児島まで出かける日々だった。一方では協会側とやり合う組合委員長もやった。
終戦間もないころ、労働運動が燃え燃え盛っていたときである。マルクスで理論武装して協会に思想闘争を挑もうとする組合幹部に対し、緒方は
「社会党も共産党もなか。組合の中で足の引っぱり合いばしなんな。大切なことは、みんなの生活を守ること。その点で一致すればよか」
緒方は委員長として協会の幹部と激しくやり合う一方で、賃上げという実を取るため幹部と酒席を共にすることもあった。最強の労働組合といわれた「炭労」(日本石炭労働組合)の全盛時代である。ほかの幹部から「ダラ幹」といわれたりしたが、要は賃上げをかち取って組合員の生活をいくらかでも楽にすべきだというのが信条だった。
石炭の斜陽化とともに石炭協会はやがて解散、緒方は貝島に帰るべきところだったが、帰ったら現場にやられそうだった。元気者という印象があったので会社は事務所に置くより石炭掘りの現場で労務者の監督をさせたがっていたからだ。緒方は現場はもう中国で卒業したと思っていた。
小西春雄協会長に相談すると、小西会長は「お前は大学は経済だろ。炭鉱よりも銀行屋が向いている」という。意外に思ったが、そうかもしれないという気もした。
小西会長は、朝鮮銀行の支店長から明治鉱業専務などを経て、戦後は九州石炭鉱業協会長、昭和二十六年から民選初代の福岡市長をした人である。
協会にいたとき、緒方は時々、小西会長の秘書役で銀行まわりなどをやっていた。炭鉱への融資を頼むわけだが、おかげで銀行業務がどんなものか、おおよそ見当はついていた。
小西春雄、貝島義之という二人の大物を保証人に正金相互銀行(現在の福岡中央銀行)に就職した。昭和二十七年、三十九歳のときだった。十八年におよぶ緒方の銀行生活が始まる。
明治大学卒業後の緒方豊吉の主な略歴は左の通りである。
昭和十三年 久留米騎兵第十二連隊入隊
十七年 宮崎房子と結婚
十八年 貝島炭鉱井径炭坑(中国)入社 労務課長代理 二十一年 引き揚げ、九州石炭鉱業協会出向 整員係長
二十六年 正金相互銀行(現福岡中央銀行)入社 庶務課 長、人事課長、柳川、中間、飯塚、西新各支店 長
三十八年 同行取締役就任 本店営業部長委嘱
四十三年 総務部長委嘱
四十四年 同行退任 泰平物産取締役会長
四十五年 同社退任 協同組合福岡卸センター専務理事
四十七年 連合会福岡流通センター専務理事
五十七年 九州盲導犬協会専務理事
五十八年 財団法人福岡盲導犬協会専務理事
六十三年 同協会理事長 現在に至る
ケンカ相手は永久の仲
正金相互銀行は、その前年、無尽会社を合併して新しいスタートを切ったばかり。新興の意気に燃えていた。
緒方は最初、庶務課長だったが、銀行は現場が大切だといわれて支店に出た。銀行といえばソロバンの時代だったが、軍隊のころおぼえた計算尺で金の計算をする一風変わった銀行員だった。
直方支店次長、大牟田支店次長、初代柳川支店長と順調に昇進する。なにせ直方は以前いた貝島炭鉱の本拠地だし、大牟田は勝手知ったる石炭の町、柳川は母の里である立花藩の城下町。地縁、血縁、人の縁で仕事はおもしろいようにはかどり、直方では在任一年で預金量を二倍に、柳川支店ではじつに六倍にした。
好成績の原因の一つは緒方の人脈の広がりだろう。
「何といっても250×3=750の味方がいる。強いよ」
何のことかと思ったら、自分がわたり歩いた明善、八女、鞍手の三つの中学の同窓生の数のことだった。それだけの友人知人が県内にいるから強いというわけだ。その中には、もちろん、かつてのケンカ相手も含まれている。
「ワルが、みんな偉うなっとった。持つべきは悪友ですな」
緒方にとって「喧嘩した奴は永久の仲」である。明大予科のころの友人、柔道四段の鈴鹿寿とはヤカンをふり上げて喧嘩した仲だが、彼が亡くなったときは京都まで出かけて葬儀委員長をやり、その息子の結婚式には親代わりで出席している。
思わぬときに友に助けられることもある。
中間支店長に着任したときのこと。前支店長と客の間でいざこざがあり、それがこじれて支店の玄関口に毎日のようにたむろしている一団があった。嫌がらせである。しかも彼らがむしろ旗を立てて本社に押しかけるといううわさが流れ、支店は弱り果てていた。
緒方が支店長室から見ていると、ひときわ威勢のよいのが先頭に立っている。八百屋だという。顔に見覚えがある。向こうもこちらを見ていたが「緒方さんじゃないですか。熊野ですたい」と親しそうに寄ってきた。
思い出した。貝島炭鉱にいたころ可愛がった男である。
「あなたが相手じゃ都合が悪い」
トラブルは一挙、解決した。
本社でもこのトラブルには頭を痛めていたが、緒方があっさり解決したので驚いた。交渉能力のある男と評価された。何のことはない相手が友人だったというだけのことだった。
「ほんとに、人間、どこで助けられるかわからないもの。友人は大切にしなければ」
相手の心をつかんで、たちまち仲良くなるという術にも長けていた。
飯塚支店長のとき、ある洗炭業者が七、八万円の金を返済しないというので家に出かけた。みすぼらしい家の裏には豚小屋がある。荒れ果てた光景だ。返済はとても無理か、と思ったが、緒方は「銀行のお金というものはね、人様から預かった大切なもので……」と説きはじめた。
最初は「儲かっとらんのだから返せない」とがんばっていた主人が「ちょっと待て」と緒方の言葉をさえぎり、席を離れたと思ったら、豚小屋から薄汚れた瓶をぶら下げて戻ってきた。密造酒である。
自分もグイッとやってから一杯飲めという。このときの味は今でも思い出すとムカッとくるという。のども焼けつくような、腐るような強烈な味だった。一杯、やっとの思いで干すと、もう一杯ときた。思い切ってあおった。頭がクラクラとした。その途端、
「よし、あんたが気に入った。今まで会った銀行の人間にはろくなのはおらんかったが、あんたは違うごつある」
そういって、主人は棚から金を取り出し、ニヤッと笑って緒方の前に並べた。川筋男の心をつかむ術を心得た支店長だった。
部下の操縦法も独特だ。
はじめて支店長を務めた柳川支店でのこと。七、八人の部下がいたが、入れかわり立ちかわり支店長の印鑑をもらいに来る。非能率と思った緒方は、部下の四つの机を四角にくっつけ、その中央に棒を立て、印鑑をゴム糸で結び付けた。使ったあと手を放せば印鑑は元の位置にもどる。四人が座ったまま用が足せる。
銀行の命ともいうべき支店長の印鑑を引っ張ったり、引っ張られたり、どう見ても銀行らしくないやり方に部下もびっくりしたが、自分たちが信頼されている証拠と支店長の株は上がった。
そこに突然、本社の臨検があった。臨検はきびしいもので、検査官が入ってきたら直立不動、一歩も動いてはいけないことになっている。検査官は支店長の隣に座った。部下が気を利かして緒方のところに印鑑をもらいに来た。だが緒方はかまわず
「いつもの通りにやってよろしい」
検査官は一瞬、唖然とした。支店長の印鑑を部下に預けっ放しにしたうえ、おもちゃ扱いしたのだから戒告ぐらい食うかと思ったが、検査官も、その報告を受けた本社からも何もいってこなかった。支店は六倍も預金量を増やしていたのだから、緒方のやり方に文句の言いようがなかったのである。緒方のやり方は例外だったが、認知されていった。
本社の営業部長になってからも次長に印鑑を預けた。何億という金を動かす取締役営業部長印である。預けられた次長は一瞬、震え上がった。悪いことをしようと思えばできるのだ。だが、もちろん貸しつぶれや不正はまったくなかった。その次長、のちに取締役になった渋田巳代治は、今でも会うと言うそうだ。
「部長は人使いがうまかったですな。あのころが一番、仕事もしたし、懐かしいですよ」
仕事は心意気
「君たちができんこつば持ってこい」
とよく言った。大切だけれど地味で神経を使う仕事。銀行はお金を扱うだけに難しい仕事が多いが、それをすすんで引き受けたので行員は仕事がやりやすく、支店の成績も上がった。
人事異動のさいは
「ほかの部長が使い切らんのを持ってこい」
骨のある人間が好きなのだ。育てれば逸材になることを知っているから。こんなことも言う。
「交際費を使い切らんやつはだめ」
交際費を節約して、いい顔するのは仕事が小さい証拠。使うべきときは会社の金を思いきり使って挑戦するぐらいの気構えがないと大きな仕事はできないということらしい。いまの銀行ではとてもと思うが、仕事は心意気という緒方の言葉らしい。なにせ「わしは銀行屋じゃない。炭鉱屋だ」が口ぐせの男なのだ。
支店長時代は
「人を見て金を貸せ」
相手の会社のバランスシートは参考資料にする程度で、あまり重視しなかった。これも人と逆。今の銀行では通用しないやり方だろうが緒方らしい。
飯塚支店長のとき、こんなことがあった。銀行の窓口に来て行員を怒鳴っている男がいる。市内の中小企業の社長で、手形の決済が迫っているのに正金本社からの融資の許可が遅れ、気が気ではないのだ。それが二、三日も続いた。社長は店内で叫び狂っている。部下に聞くと、仕事一本の熱血漢という。緒方は思いついた。
本社の許可は前日に下りていた。だが緒方はそれを伏せておいて社長を支店長室に招き入れた。
「あなたを信じ、支店長の責任でお貸ししましょう」
社長は歓喜した。
「本社がしぶっているのに支店長が自分を信じてくれた」
社長は以来、正金のいい顧客になり、緒方の友人にもなった。
この一件、「うそも方便」というところだが、従業員のために必死になっている社長の人間を見抜いて、「この男なら金が生きる。むしろ自分の判断で貸そう」と思っての演出だったろう。バランスシートより人間を見る。緒方の人の心のつかみ方を、かいま見せる話である。あとでタネあかしをして社長と大笑いしたという。
中間支店長から営業部次長として久しぶりに本社に帰ったが、労働組合ができると「組合と渡り合えるのは緒方しかいない」ということで人事課から拡充された人事部の初代部長に就いた。
このころ正金相互では労働争議が原因で役員が総退陣する事態が発生、西日本相銀から鶴喜代二副社長が送り込まれ、社長に就任した。緒方はこの鶴社長にたいへん可愛がられた。気性が合ったのだろう。緒方も鶴社長を“おやじ”と呼んで尊敬した。
緒方は、このあと飯塚、西新の二つの母店支店長を経て取締役営業部長になった。二十人近い先輩を飛び越えての抜擢だった。それまで同行の役員はすべて他行から迎えており、社員から昇格して役員になったのは緒方が最初だった。
選挙応援する支店長
バンカー緒方は、たしかに型破りだが、それは無策の策というべきものだったろう。「おれは炭鉱屋だ」といって数字の世界に情を持ち込み、人情に訴えて成績を上げていく。他の銀行マンが、ちょっと真似のできない芸当をやる。大銀行なら、とても出世はできなかったろう。
飯塚支店長のときの捨て身の戦法は、いまも語りぐさだ。
昭和三十年代の半ば、飯塚市の渡辺鉱業社長、渡辺本治氏が衆議院福岡二区から打って出たとき。飯塚の各支店長は「一党一派に偏るまい」と推薦を見送ったが、緒方は考えるところがあって、ただひとり応援した。
それも応援カーに乗って「渡辺をよろしく」と演説をぶちまくったのである。渡辺候補を同伴して飯塚支店管轄の各支店まわりもやった。銀行が、しかも一介の支店長が表面に立って特定の候補の応援演説をぶつなんて考えられないことだった。一歩間違えば首はない。
渡辺はトップ当選した。だがお返しがない。半年後に国会が明け、飯塚に帰った渡辺が緒方を自宅に招いた。お土産にジョニクロ二本をくれた。「これが腹をくくってやった選挙応援の見返りか」と心中ぼやいていると、帰りぎわ、渡辺が手にあまるほど大きい紙包みをかかえてきた。千円札の束である。開くと三千万円。今なら四、五億か。「これは当選御礼ではありません。正金相銀への預金です」。札束は車で支店の金庫に収められ、定期預金になった。
もっと大きい収穫があった。緒方は選挙事務所に日参したが、そこには地元の会社社長や炭鉱主がわんさとたむろしている。金持ちばかりだ。彼らが「あんたは、ほんま面白か支店長じゃな。ま、一杯やりなっせ」と近づいてきて顔なじみに。これが大いに預金獲得に結びついた。そのときになって初めて、ほかの支店長は緒方が選挙に熱を上げた魂胆に気づいたのである。
銀行生活も、もう三十余年の昔になったが、銀行のあり方について
「いまの銀行は何ですか。自分の利益ばかりで。たしかに時代は違うけれど、私たちのころは、もっと気概みたいなものがあった」
自分がお世話になった世界のことだから批判の言葉は少ないが、最近の金融機関をめぐる不祥事には我慢ならないようである。
難事業への挑戦
昭和四十五年、緒方は銀行生活にピリオドを打ち、一大事業に取り組むことになった。福岡流通センターの建設である。
四十年代の福岡市は年ごとに増える自動車で、いたる所で交通が乱れていた。加えて土地の高騰。市内店屋町の繊維業ををはじめとする卸し商は店舗を広げようにも土地はなく、駐車場もままならない。商品の輸送も満足にできない状況だった。
卸し業と運輸、倉庫が三位一体となって機能的な営業ができる新天地を求める機運が満ちていた。福岡市や県も市街地再開発や交通公害の解消の立場から、この運動を支援した。
こうして多々良川沿いの福岡市東区多々良地区に市街地流通整備法にもとづく大流通団地を建設する計画が具体化し、福岡流通センター建設協議会が発足、緒方はその専務理事という激職に就くことになった。
総事業費二百八十億円、二十五万坪。ここに各業者を移転させるのだから大事業、難事業である。国、県、市、金融機関との交渉、調整。業者間の利害の調整だけでも大変な仕事だった。
着工間もなく、オイルショックに見舞われた。建設費が最初の見積もりより二割、三割、遂には倍増した。金が足りない。緒方は明治大学の先輩、三原朝雄代議士に頼み込み、福田赳夫蔵相を紹介してもらった。大物大臣の前で緊張して窮状を訴えたのを覚えている。大蔵省の壁の厚さをいやというほど味わったが、なんとか商工中金から資金を借りることができた。
中小企業の苦しさを身にしみて感じていたから、あの人たちのためになるなら、と文字通り、骨身を削って働いた。やりがいもあった。
センターは約三年ののちに完成した。
感慨深いものがあった。正金相銀にいたとき若戸大橋の開通式に出席した。そのとき隣のヘルメットの男性が、肩車をした幼いわが子に「よく見なさい。この橋はお父さんが造ったんだよ」と話しかけるのを目撃したことがある。いつの日か自分も生きた証として、自分の作品を形として残したい。その思いがかなえられて、いい気分だった。
昭和五十年十二月九日の盛大な完成式で司会をつとめた緒方は、一千人を超える参加者を前にして
「菊花ただよう今日の佳き日……感無量でございます。……今まさに竜はみごとに書き上がりました。ここで亀井知事に竜の目玉を入れていただきましょう」 いくぶん高ぶった気持ちで開会のあいさつをしたことが昨日のことのように思い出される。
亀井知事の祝辞を聞きながら、この仕事に追われる最中に亡くした二女恵子のことを、しきりに思い出していた。
恵子は三年前の交通事故で東大病院に入院していた。上京の折は何回か見舞いにいったが、忙しくて側にいてやれないことが苦にもなっていた。そこに突然の訃報だった。
死に目に合えなかったのは残念だが、娘も許してくれるだろう。自宅でささやかな葬式をと考えていたのに流通センターの人たちをはじめ二百数十人もの人が参列、盛大なものになった。
まだ年若い娘を失った悲しみは大きかったが、自分が仕事に心血を注いでいる姿を見てきた人たちが、こんなに多数参列してくれたことが涙が出るほどうれしかった。
緒方に「あなたが一番影響を受けた人はだれか」と尋ねると
祖父正直
貝島義之
鶴喜代二
の三人を挙げる。
祖父正直からは、人としてしてはならないことを習い、ライオンズの貝島社長からは人は社会に奉仕すべきだということを教わり、おやじと呼んで尊敬する鶴社長からは筋を通した対人関係を勉強したという。
流通センター建設の仕事にたずさわり、最後まで責任を全うした緒方は、少しでも世間の役に立てたことを喜び、今日の自分を作ってくれた三人にいくらか恩返しができたと、いささかの感慨があった。
しかし、まったく方向違いの大仕事が、この後に待っているとは予想もしなかった。
 次のページへ。
次のページへ。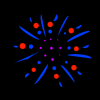 目次へ戻る。
目次へ戻る。 トップページへ戻る。
トップページへ戻る。★ Copyright(C) 2001-2006 無断転載を禁じます
。